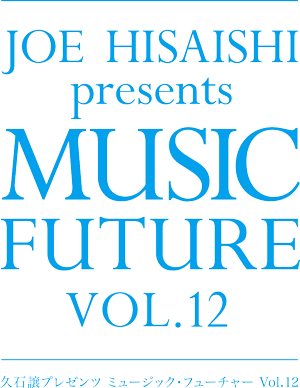第6回 Young Composerʼs Competition
受賞者決定!
100作品を超えるご応募をいただき誠にありがとうございました。
優秀作品に選ばれたのは、
Luca Pettinato さん作曲 "Fiore di un giorno"です。
優秀作品は、MUSIC FUTURE Vol.12 東京公演にて18:30より世界初演いたします。
※開場時間内の演奏になりますので、ご入場の際にはご配慮をお願い申し上げます。
審査員のニコ・ミューリーさんからは動画メッセージも届きました。
優秀作品に選ばれたのは、
Luca Pettinato さん作曲 "Fiore di un giorno"です。
優秀作品は、MUSIC FUTURE Vol.12 東京公演にて18:30より世界初演いたします。
※開場時間内の演奏になりますので、ご入場の際にはご配慮をお願い申し上げます。
審査員のニコ・ミューリーさんからは動画メッセージも届きました。
音源はこちらからお聴きいただけます。※音源は冒頭のみ
◆第6回Young Composer’s Competition優秀作品
Fiore di un giorno
作曲:Luca Pettinato
- Luca Pettinato
- 1989年、イタリア・マントヴァ生まれ。故郷の音楽院で作曲の学位を、トレント音楽院で吹奏楽オーケストラの学位を取得。2013年、エンニオ・モリコーネが委員長を務めた国際宗教音楽作曲コンクール「ベネデットXVI」で2位。2010年よりマントヴァのガゾルド・デッリ・イッポリーティ吹奏楽団の指揮者、2017年よりヴェローナのディーノ・ファントーニ吹奏楽団の指揮者を務めている。2022年のフリコルノ・ドーロ国際吹奏楽コンクールでは、ガゾルド・デッリ・イッポリーティ吹奏楽団が第3部門で1位、ディーノ・ファントーニ吹奏楽団が第2部門で1位を獲得。これらの功績により審査員特別賞を受賞した。コンサートバンド作品はScomegna Edizioni Musicaliから出版されている。
審査員講評 ※五十音順
一貫した筆致を作品としての完成度の高さと評価した。作品全体から感じられる知性にも好感。
足本 憲治(国立音楽大学准教授)
限られた音の選択でのヒーリング風の音響が美しい!クラリネットの重音やハーモニクスが極めて効果的に使用されているし、重音の比重を揺らす書き方が演奏していて楽しそう。ゆらぎがあるがパルスを失わない効果的な書法。ピアノのプリパレーションの音響も美しい(ちょっとチェンバロのようで)。
鈴木 優人(指揮者・作曲家・鍵盤奏者)
短いフレーズをずっと積み重ねていく方法で、全体の構成、それから方向がブレていないという意味では、とても完成度の高い作品だと思います。書き方も含めて、隙のない、過不足のない、とても良い作品だと思います。ただ、特殊奏法にそれほど頼る必要はないのではないか。木管楽器その他に出てくる特殊奏法に関しては、そのような音響効果にもう少し走らずに書いても十分成立する楽曲だと思います。この方向でこの作家の他の曲も聞いてみたいです。
久石 譲(作曲家)
工夫された音色の繊細さ、「起承転結」をはっきり打ち出した形式感は、この曲が「さらそう樹」の開花の絵画的表現かどうかを問わず、ミニアチュアとしてそれなりに完成していると感じた。であるからこそ、第76小節からの「転」が――「平家物語」のさらそう樹から連想される「諸行無常」の表現とはいえ――音楽的にはあまりにも唐突で物足りない。
前島 秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)
非常に良い作品だと思います。技巧的でありながら落ち着きがあり、拡張奏法のすべてが曲の要素と完全に結びついていて、恣意的なところが全くありませんでした。曲がゆっくりと丁寧に展開していく点もとても良いです。ジェスチュアル(身振り的)な印象がありつつも、ピッチへの細やかな配慮が感じられました。全く機械的でなく、常に自然で有機的に感じられました。
ニコ・ミューリー(作曲家)
一次審査通過作品 ※音源は冒頭のみ
still... fast
作曲:Jaemin Jung
良い雰囲気の作品。よく練られているが展開の手法に常套句的なものを感じる点は惜しい。
足本 憲治(国立音楽大学准教授)
ピアノの中でのダイナミクスの書き分けは、演奏上の完全な実現が難しいかと思った。また弦楽器の重音の部分も少々難しすぎるのでは。Ad lib. と言っても、リズムをここまできっちり書かれると無視するのも難しい。しかし、それが「苛烈さ」を表現していると言うのであれば成功しているかもしれない。Jのセクションは一番魅力的に感じたのは、それまでの「苛烈さ」の所以か。その後、Kのセクションは全体から見て短すぎるように思う。
鈴木 優人(指揮者・作曲家・鍵盤奏者)
大変よくできたスコアです。とても技術力の高い譜面で、説得力のあるノーテーションですが、ルチアーノ・ベリオやルイジ・ノーノのようなイタリア系の昔の現代音楽家の書いた作品の譜面への近さを感じます。いわゆる普通の現代音楽的な書き方に似ていて、よく書けてはいるのですが、例えば、音も非常に見事に配列している割には、変化が乏しいと思います。響きの変化が乏しいことと、動いているわりには音が不自由にも感じます。例えば、Jからのバイオリンとチェロの動き。そこからずっと同じ6連符で繰り返しますが、この辺りもただただ同じにしてしまうよりはもう少し変化があったほうが良いと僕は感じます。で、その後Kには変化がつきますが、その段階では非常にインプロビゼーション的な、演奏者にゆだねた記譜法に変化する。ここまで緻密に書くならば、そのまま音符を書いていったほうが良いのではないかという気がします。これは作曲家が必ず陥る大きな問題ですが、譜面上で成立する完成度というのと、実際の音の完成度は違うということで、この作品はやや譜面が勝っている。これだけの高度な技術を持っている人なので、もう少し現実の音としての変化と、ノーテーションとしての楽譜の整合性とを意識されたら、より高いレベルで完成するのではないかと期待できます。
久石 譲(作曲家)
几帳面に書かれた前半部のスコアは、それ自体が雁字搦めの現代の緊張感を表現していると言える。エピローグで音楽を弛緩させるクラリネットも美しい。が、[E]のセクションで現れる「悲鳴」が現代人の「苦悩の叫び」だとするならば、このような中途半端な表現でなく、さらに工夫してほしかった。戯画的にするのか、もっと音楽的に突き詰めるのかは、ともかくとして。
前島 秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)
この作品のリズム感覚にはとても感銘を受けました――非常に正確で、よく考えられています。作曲家はプログラムノートを非常によく反映していると思いますが、そこで私が疑問に思ったのは「なぜこれが音楽作品である必要があるのか」という点です。曲がジェスチュアルなもの(あるいは音形として受け取られるべきなのか、それとも個々の音として受け取られるべきなのかが、しばしばはっきりしないように思いました。同じ音の塊の中にしばらく留まっているように感じられるのは、たとえそれが作品の意図だとしても、私にとってはやや心地良くない印象があります。しかしリズムの書き方は非常に高度で、とても緊張感があり、刺激的です。
ニコ・ミューリー(作曲家)
rot
作曲:Florijan Jelen-Lörnitzo
一つ一つのジェスチャーの意図が明確で引き込まれる。「書く力」の高さを評価したい。
足本 憲治(国立音楽大学准教授)
面白い!火山や炎の描写のページは思わず笑ってしまった。図形楽譜の絵も上手!演奏上もアンサンブルを楽しめる要素が満ちていて、そのせいか音源の演奏も素晴らしい。コダーイ風?の少しメランコリックなセクションも美しい。(最近の高級なピアノは蓋をバン!と閉められないので、それが実演上の問題か)。楽譜を見ているほうが聴いているより面白いかも。
鈴木 優人(指揮者・作曲家・鍵盤奏者)
全体に、楽曲としてのまとまりはあると思います。音自体のあたたかさがあり、そういう意味ではとても好感の持てる作品ですが、ちょっと音響効果に走ってしまっている傾向を感じます。
たとえば、冒頭の音符と線の書き方はどうしても演奏者に委ねるところが多くなる。ある区間を10秒で演奏するというタイム表記をすると、演奏者は基本的に1拍イコール60、要するにテンポ60で数えてしまう。なので、場合によってはもっと細かく譜面で指定する普通の譜面の書き方の方がいいところも出てきます。
また、ある程度演奏者に委ねた書き方の延長として図形楽譜が出てきます。僕はテリー・ライリーの譜面を想起して面白く感じますが、これは相当、演奏家に委ねてしまう。テリーさんは即興演奏が主体の人なのでそのような「イメージ」の譜面でいいですが、楽曲として伝えていくとするならば、これでどのくらい演奏者に伝わるか、というのは考えた方がいいと思います。
それから、同時に楽器を叩くといったところがたくさん出て来ますが、それも踏まえると全体に音響効果に走ってしまっているところがある。もう少し音と音の強固な結びつきや構成を想定された方が今後良いのではないかという感想を持ちました。
ただ、もう一度言いますが、全体の作品のまとまりや、曲の温かみ、全体が成立している過程にはとても好感が持てます。
たとえば、冒頭の音符と線の書き方はどうしても演奏者に委ねるところが多くなる。ある区間を10秒で演奏するというタイム表記をすると、演奏者は基本的に1拍イコール60、要するにテンポ60で数えてしまう。なので、場合によってはもっと細かく譜面で指定する普通の譜面の書き方の方がいいところも出てきます。
また、ある程度演奏者に委ねた書き方の延長として図形楽譜が出てきます。僕はテリー・ライリーの譜面を想起して面白く感じますが、これは相当、演奏家に委ねてしまう。テリーさんは即興演奏が主体の人なのでそのような「イメージ」の譜面でいいですが、楽曲として伝えていくとするならば、これでどのくらい演奏者に伝わるか、というのは考えた方がいいと思います。
それから、同時に楽器を叩くといったところがたくさん出て来ますが、それも踏まえると全体に音響効果に走ってしまっているところがある。もう少し音と音の強固な結びつきや構成を想定された方が今後良いのではないかという感想を持ちました。
ただ、もう一度言いますが、全体の作品のまとまりや、曲の温かみ、全体が成立している過程にはとても好感が持てます。
久石 譲(作曲家)
本来ならば、この曲は今回した審査した他の3曲とは別の基準で審査されるべきだろう。パート譜の作成が不可能な図形楽譜、規定の7分を大幅に超えた演奏時間、しばしば単調に陥りがちな表現、チェロの過剰な負担など、この曲が抱える問題点を挙げたらキリがない。それでもこの曲を第1位に挙げたのは、曲名の「rot(赤)」というよりは「Schwarzemagie(黒魔術)」と呼ぶべき呪術的な魅力が、一度聴いたら忘れられないのと、この曲の存在が作曲審査という行為に対するひとつの問題提起と感じたからである。本能的に書き上げた音楽から聴こえてくる、表現への強い意志は、この曲の図形楽譜に書かれた火山の噴火と同様、無理に抑えつけることはできない。図形楽譜はともかく、ドイツ語の演奏指示は明確なので、演奏不可能ではないと思う。
前島 秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)
たくさんのアンサンブルに演奏してもらいたい、本当に素晴らしい作品です。随所で驚かされましたが、特に26ページはとても楽しめました。拡張された記譜のドラマ性もとてもよく機能していると思いました。
唯一感じたのは、音形の間にもっとドラマがあっても良いのでは、という点です。要素に入り込むと本当に素晴らしいのですが、しばしば「ここは移行部分だな」と強く意識してしまいました。
私の感覚では、この作品は10〜11分よりも8〜9分の曲にするのが良いのではないかと思います。移行部分を少し工夫すれば、さらに素晴らしい作品になるはずです。
唯一感じたのは、音形の間にもっとドラマがあっても良いのでは、という点です。要素に入り込むと本当に素晴らしいのですが、しばしば「ここは移行部分だな」と強く意識してしまいました。
私の感覚では、この作品は10〜11分よりも8〜9分の曲にするのが良いのではないかと思います。移行部分を少し工夫すれば、さらに素晴らしい作品になるはずです。
ニコ・ミューリー(作曲家)
MCHNS
作曲:Massimo Voltarel
ストーリーの運びに確かな力を感じる。生演奏で聴いてみたいと最も思わされた作品。
足本 憲治(国立音楽大学准教授)
ピアノのマレットで叩く持続音の効果は面白い。和風の渋みを感じる一曲。ヴィオラのスル・ポンティチェッロ奏法がまるで尺八のように聞こえた。ただ、プリパレーションの仕方を含め、全体として書法は実験的とは言えないように思う。
鈴木 優人(指揮者・作曲家・鍵盤奏者)
eBowという特殊な装置を使った発想は面白いですが、全体に、やや音響効果的なところがあると思います。全体の音の構成がまだよく見えないので、もう少し練った方が良いのではないでしょうか。音の動きがある意味非常に単純になってしまっているため、ピアノの内部奏法を含めてある種の音響の効果で楽曲を成立させてしまったところを少し感じます。そこがもったいないので、逆に、途中に繋ぎのいろいろな音形が出てくるところの継続していく変化の部分が少し足りなく感じます。
それから、例えば練習番号のD以降で冒頭と同じ響きが再現されますが、これが出てくると全体が単純に3部構成としてまとまった非常に古典的な方法に聞こえてしまう。そのあたりももう少し工夫をする必要があると思います。
クラリネットとヴィオラとピアノを使った楽器の編成からすると、音の構成にもう少し力を注いだらとても良い作品になる可能性が高いので、今後もこういう編成、あるいは、これに準じるシリーズを書いていってもらうといいと思います。期待しています。
それから、例えば練習番号のD以降で冒頭と同じ響きが再現されますが、これが出てくると全体が単純に3部構成としてまとまった非常に古典的な方法に聞こえてしまう。そのあたりももう少し工夫をする必要があると思います。
クラリネットとヴィオラとピアノを使った楽器の編成からすると、音の構成にもう少し力を注いだらとても良い作品になる可能性が高いので、今後もこういう編成、あるいは、これに準じるシリーズを書いていってもらうといいと思います。期待しています。
久石 譲(作曲家)
コンベンショナルなトリオ編成という「伝統の機械的繰り返し」に反抗し、Cl、Va、プリペアドピアノという斬新な編成で試みられた音響と共鳴の実験が非常に興味深く、面白い。しかしながら、中間の[C]のセクションのガムラン風の表現が、その前後のセクションの独創性に比して、ややステレオタイプに感じられた。それこそ「機械的 mechanical 」ではないか?
前島 秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)
この作品のプログラムノートはとてもよく書かれていると思いますが、音楽そのものにはあまりドラマ性を感じられませんでした。曲のどの部分をどこに置いてもほとんど印象が変わらないのではないかと思います。ある意味でこの作品は、(とてもかっこいい!)音の集成のように感じられました。プログラムノートには「音の状態が連続して変化していく」と書かれていますが、転換部分の展開に興奮する瞬間(例えば練習番号Cに向かうあたりなど)があっても、77~78小節のように空白の小節があると、思わず意識が逸れて思考が他に向いてしまうことがありました。
こうした転換部分をもう少し引き締めることが、この作品を本当に素晴らしいものにする鍵だと思います。
こうした転換部分をもう少し引き締めることが、この作品を本当に素晴らしいものにする鍵だと思います。
ニコ・ミューリー(作曲家)